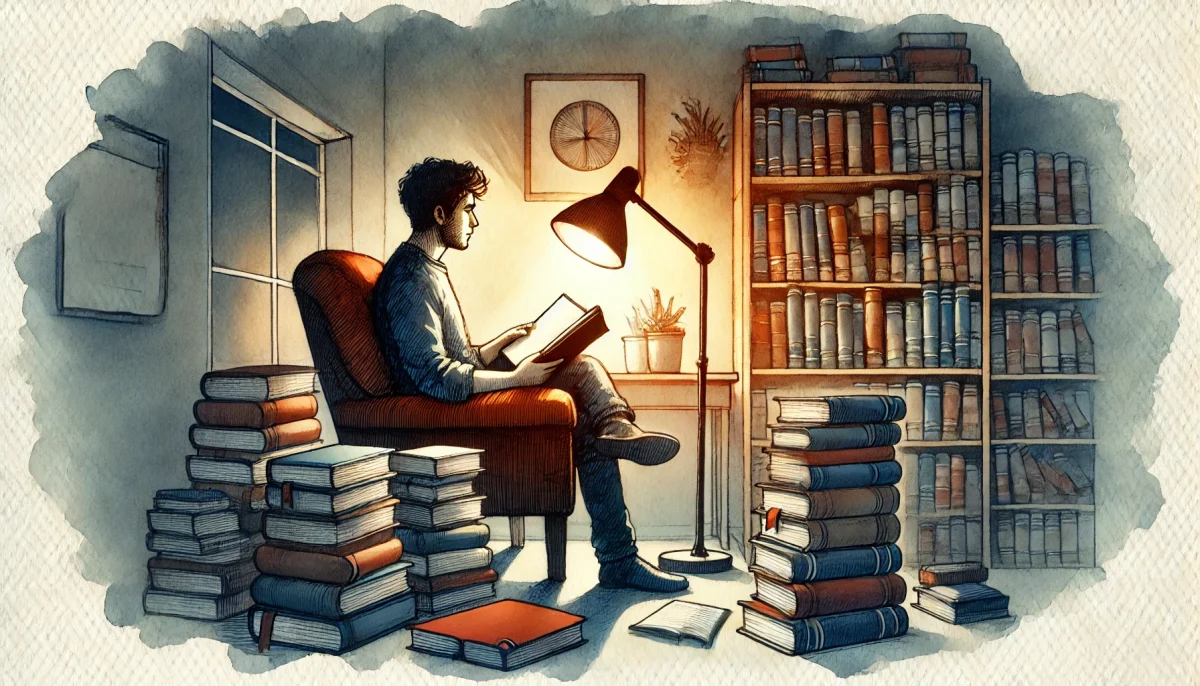
論理的なるもの
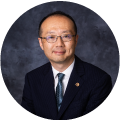 弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.03
弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.03
読書をしていると、ときに「まさに目からウロコ!」という一冊に出会うことがあります。そういった本との出会いは、人生の大きな楽しみのひとつですよね。今回ご紹介するのは、まさにそのような一冊。『論理的思考とは何か』です。
「論理」という言葉には、少し難しい印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、本書は著者の文章力の素晴らしさもあり、とてもわかりやすく書かれています。
そもそも、論理というのは私たちの生活に深く根ざしているものです。特に、弁護士にとって論理は仕事の基礎とも言えるもの。論理的に物事を整理できなければ、交渉も裁判も成立しません。私自身、大学時代に一般教養として論理学を学んだことがあります。当時は論理学とは何かもよくわかっておらず、教科書を読むのも苦労しましたが、時間をかけて学ぶうちにその面白さに引き込まれていきました。
私たちは、論理的であることを「世界共通の正しさ」として捉えがちです。しかし、本書を読むと、それが実は文化の影響を大きく受けていることがよくわかります。著者は、論理のあり方が文化ごとに異なることを、代表的な4つのパターンを挙げて説明しています。
これまで当たり前だと思っていたことが、実はそうではないと知ること。これはまさに「学ぶ」ということではないでしょうか。
ときどき、「日本語の文章は非論理的で情緒的だから、アメリカ的な書き方(結論先出しの論理展開)が優れている」といった意見を目にします。しかし、本書によると、日本語の文章もまた一つの論理体系に基づいているのです。
アメリカ的な文章は直線的で、目的に対して最短距離を示すスタイル。一方で、日本の文章は紆余曲折を経ながら結論に至るものです。これは、結論を急がず、多面的に考えを巡らせることを重視しているからかもしれません。
近年、私たちは効率を求めすぎるあまり、難しい問題や複雑な課題に対しても、単純な結論を急いでしまう傾向があります。しかし、本当に重要な問題に対しては、時間をかけてじっくり考えることも必要なのです。結論を出さないこと、棚上げすること、先送りすることも、場合によっては論理的な解決策のひとつかもしれません。
本書を読んで改めて感じたのは、視点を増やすことの大切さです。私たちは一つの価値観に縛られがちですが、異なる文化の論理を学ぶことで、より広い視野を持つことができます。
論理とは何か?それを文化の観点から考えると、新しい発見があるかもしれません。ぜひ、手に取って読んでみてください。
CONTACT
お困りごとは、島田法律事務所で
解決しませんか?
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
オンライン相談をZoomでも対応しています。
083-250-7881
[9:00〜17:30(土日祝日除く)]


![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)
![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)