
「“ためらう”という優しさを忘れない」
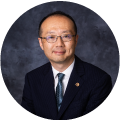 弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.30
弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.30
最近、メディアの報道やSNSの発信を見ていて、ふと思うことがあります。それは「ためらう」という感覚が、少しずつ社会から薄れてきているのではないか、ということです。
「ためらう」という言葉には、どこか消極的で後ろ向きな印象があるかもしれません。でも私は、それが必ずしも悪いことではないと思っています。以前にもブログで似たような話を書いた気がしますが、自分の思っていることや感じていることを、なんのフィルターもかけずにダイレクトに発信することが「個性」とされ、それが肯定されすぎているように感じることがあります。
人の内面というのは、美しいものばかりではなく、時にはグロテスクだったり、生々しかったりもします。そうした「ありのまま」を常にさらけ出すことが、果たして本当に正しいのでしょうか。誰かに強い言葉を投げつけることが「正直」で、それを受け止められない人は「弱い」と片づけられてしまうのは、やはり苦しい社会だなと思います。
だからこそ、私は「ためらう」ということを、もっと大切にしてもいいと思うのです。言いたいことがある。でもそれを言う前に、「これを言ったら相手はどう感じるだろう」「本当に今、言うべきことなんだろうか」と一呼吸おく。その一瞬の逡巡こそが、相手への思いやりであり、社会の中で共に生きるための知恵だと思うのです。
もちろん、何も言わずに我慢し続けることが良いとは思いません。ただ、「ちょっと立ち止まって考える」という行為を、もっとポジティブに捉えてもいいのではないでしょうか。
最近では、遠慮せずに「豪速球」を投げつけるような言い方が「正しさ」とされてしまっているように感じます。そうした言葉を受け止められる人は、実際はほんの一部で、大半の人はその衝撃に傷ついてしまいます。けれど、傷ついたと声をあげることさえも「弱い」と見なされる。そうやって、ますます声を出しづらくなっていく──。この10年、20年で、そんな光景が随分と増えたように感じます。
「ためらう」ことは、相手を尊重すること。自分の考えを持ちながらも、他人の考えに想像力を働かせること。私は、それこそが本当の意味での「個性」だと思うのです。
自分の思いだけをぶつけ合うのではなく、みんなが少しずつ調整しながら、社会という大きな仕組みを成り立たせていく──そんな優しさやバランス感覚が、これからもっと求められてくるように思います。
CONTACT
お困りごとは、島田法律事務所で
解決しませんか?
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
オンライン相談をZoomでも対応しています。
083-250-7881
[9:00〜17:30(土日祝日除く)]


![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)
![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)