
「介護が引き起こす“共倒れ”を防ぐために」──経営と暮らしの両立に向き合う
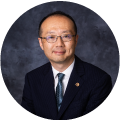 弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.28
弁護士:島田 直行
投稿日:2025.03.28
最近、経営者の方から受ける相談の中に「社員の介護」に関するものが増えてきました。特に、中小企業では人手不足が深刻化している中で、社員が家族の介護と仕事の両立に悩み、業務に支障をきたすケースが目立ってきています。
介護は誰にとっても無縁ではありません。年齢を重ねれば、いつかは誰かの世話が必要になる。今、まさに40代・50代の働き盛りの世代が、親の介護を担う立場になっているのです。しかし彼らは、企業にとっても中心的な戦力。そんな人材が介護のために長期的に離脱してしまうと、事業運営に大きな影響を与えかねません。
「親の介護はしたいけれど、生活のためには働かなければならない」──そんな思いを抱える方がたくさんいます。ですが、介護というのは、愛情だけで乗り切れるものではありません。制度の知識がなければ支援の受け方もわからず、慣れない介護の現場で心身ともに疲弊してしまう。地域包括支援センターやケアマネジャーといった言葉を聞いたことがあっても、「何をしてくれる人なのか」と問われて即答できる方は少ないのではないでしょうか。
それに、どれほど社会福祉制度が整っていても、無償で受けられるサービスばかりではありません。介護と仕事の両立には、時間もお金もかかります。現実的に考えると、社員が介護を担う上で最初に必要なのは、「調べたり、相談したりするための時間」を確保できることなのかもしれません。ケアマネとの打ち合わせすらできないような忙しさでは、制度の活用もままならないのです。
企業にとっても、これは他人事ではありません。退職という最悪の選択を避けるためにも、介護に関わる時間を認める社内の雰囲気づくりが何より大切です。制度的な支援が難しい場合でも、「その時間はとってもいいんだよ」と伝えられるだけで、社員にとっては大きな支えになります。
最近、私が読んで特に印象に残った本に『上司に「介護始めます」と言えますか? ~信じて働ける会社がわかる』という一冊があります。介護制度の基本だけでなく、それが企業経営にどのように影響を与えるのか、という視点で整理されており、とても参考になりました。事業を担う経営者の皆さんには、ぜひ一読いただきたい一冊です。
この本を読みながら改めて感じたのは、介護はときに人の暮らしや仕事を巻き込んで“共倒れ”を引き起こすほどの力を持っている、ということです。だからこそ、どこかで踏みとどまるポイントを持つことが必要です。そしてそれは、企業における「制度」や「仕組み」のあり方と深く関わっているのだと思います。
これからますます「企業経営と介護」は切り離せない関係になっていくでしょう。社員一人ひとりの暮らしを尊重しつつ、企業としてどう支えるのか。みんなで知恵を出し合いながら、誰にとっても働きやすく、暮らしやすい社会を目指していきたいと思っています。
CONTACT
お困りごとは、島田法律事務所で
解決しませんか?
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
オンライン相談をZoomでも対応しています。
083-250-7881
[9:00〜17:30(土日祝日除く)]


![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)
![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)